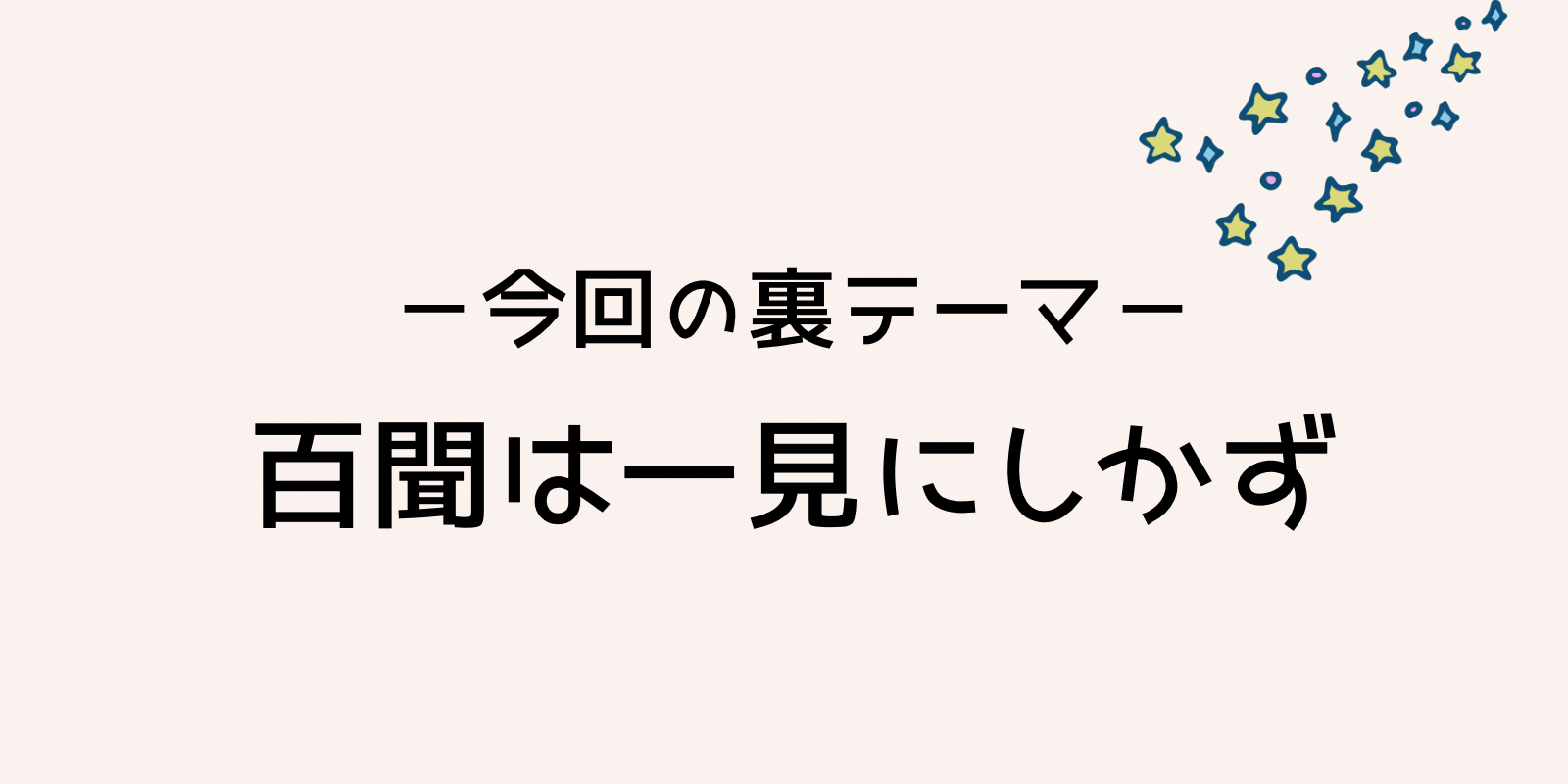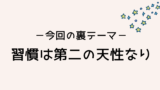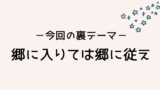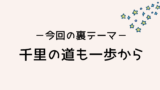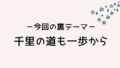マーケティングは「価値を届ける仕組みづくり」
「マーケティング」と聞くと、広告や営業活動を思い浮かべる人が多いかもしれません。
しかし、マーケティングは単なる広告や販売促進にとどまらず、「商品やサービスを必要としている人に適切に届けるための一連の活動」を指します。
つまり、「患者さんに適切な医療を届ける仕組みをつくる活動」 なのです。
医療機関におけるマーケティングは、一般企業のマーケティングとは異なる点が多く、法律や倫理の観点から制約も多いのが特徴です。
そのため、単に「広告を出せばよい」「SNSで発信すればよい」というわけではなく、適切な戦略が求められます。
この記事では、未経験の医療マーケターがマーケティング活動を始める道しるべとなる以下のポイントを分かりやすく解説します。
- 医療機関にマーケティングが必要な理由
- マーケティングの基本
- 最初にやるべきこと
- 医療機関ならではのマーケティング戦略
- 医療マーケティングの注意点
- Google(SEO)の重要性
- 実践時の注意点
マーケティングとは?広告や営業とは違う仕組みづくり
「マーケティング=広告や営業」ではない!
マーケティングを始めると、最初に混乱するのが「マーケティングと広告や営業の違い」です。
| 種類 | 考え方 |
|---|---|
| 営業活動 | 直接、患者さん(お客さん)に診療を受けてもらうための活動。 マーケティングが設計した戦略の一部。 |
| 広告 | 診療内容や病院の強みを広めるための手段。 マーケティングの一要素にすぎない。 |
| 広報(PR) | クリニックのイメージ向上や信頼を築くための活動。 マーケティングと連携するが、目的が異なる。 |
マーケティングとは、単なる広告や営業だけではなく 「患者さんに適切な医療という価値を届けるための活動全体」 です。
よりわかりやすい言葉にすると、「どうすればお客さん(患者さん)がサービスを見つけ、選び、利用し続けてくれるか?」を考え、仕組みを作ることです。
例えば、クリニックの場合:
- どんな患者さんに来てほしいか?(ターゲット設定)
- その患者さんが何を求めているか?(ニーズの把握)
- どうやってその患者さんにクリニックの存在を知ってもらうか?(情報発信・広告など)
- 来院後に満足してもらい、また来てもらうには?(サービス改善・口コミ対策など)
といった患者さんの「知る→選ぶ→利用する→リピートする」までの流れを設計し、最適化することを指します。
医療機関におけるマーケティングの重要性
患者さんの選択肢が増えている
昔は「家や職場の近くの病院に行く」のが普通でしたが、今はインターネットで比較して病院を選ぶ時代になりました。
- 「めまい クリニック」 などの検索結果を見て選ぶ
- Googleのクチコミや評判を確認する
- 公式サイトの情報をチェックする
こうした行動が一般的になったため、適切なマーケティングを行わなければ、新しい患者さんに来院してもらうのが難しくなっています。
競合との差別化が必須
都市部では同じ診療科のクリニックが複数あるのが当たり前です。
そのため、以下のような強みを明確にすることが大切です。
| 例 | 差別化のポイント |
|---|---|
| 頭痛専門の病院 | 「MRI即日検査」「片頭痛治療専門外来」などの特色をアピール |
| 訪問診療を行うクリニック | 「エリア内なら24時間365日対応」「認知症ケアに強い」などを明示 |
「どこでもやっている診療」ではなく、自院ならではの強みを伝えることが、医療マーケティングの重要な役割です。
医療マーケティング初心者が最初にやるべき3つのこと
現状を把握しよう
マーケティングの本を読んでも、「具体的に自分の職場で何をすればいいのか分からない…」と感じる人も多いでしょう。
そんなときは、まず 「今の状況を整理する」 ことが重要です。
✅ ターゲット(患者さん)はどんな人?
→ 年齢層、性別、主な疾患、来院の理由などを把握
✅ クリニックの強みは何か?
→ 「他院と違う点」や「患者さんに選ばれている理由」を整理
✅ どんな集患施策をしているのか?
→ ホームページ、SNS、チラシ、Google広告などの有無を確認
✅ 現在の課題は何か?
→ 「患者数が減っている」「新規患者が少ない」「特定の診療科が伸び悩んでいる」など
目標を設定しよう
現状を把握したら、次に考えるのは 「何を目標にするのか」 です。
例えば、
- 新規患者を増やす → SEO(Google検索)やGoogleビジネスプロフィールを強化
- リピーターを増やす → LINE公式アカウントや予約システムを活用
- 診療科ごとの患者層を広げる → ターゲットに合った情報発信を強化
といったように、目指す方向を明確にすることで、マーケティングの方針が決まります。
できることから小さく実践しよう
未経験者が一番陥りがちなのが、「何から始めればいいか分からず、動けない状態」です。
マーケティングは実際にやってみないと分からないことも多いため、小さくてもいいので、実際に施策を試してみることが大切です。
例えば、
✅ Googleビジネスプロフィールを最新情報に更新(無料でできる!)
✅ ホームページのお知らせを1つ投稿する(操作に慣れる)
✅ 診療内容ページを見直し、分かりやすく改善する
このように、できることから始めることで、「何が効果があるのか」「どこを改善すべきか」が少しずつ見えてきます。
SEOとは?広告なしで患者さんに見つけてもらう方法
SEOの重要性
GoogleやYahoo!などの検索エンジンで自院のホームページが上位に表示されるように工夫する施策のことです。
例えば、患者さんが「頭痛 外来 〇〇市」と検索したときに、自院のホームページが上位に表示されれば、より多くの人に見てもらえます。
SEOのメリット
日本では検索エンジンの75〜80%がGoogleを利用しており、Yahoo!の検索もGoogleのシステムをベースにしています。
つまり、GoogleのSEO対策をすれば、Yahoo!にも効果があるということです。
SEO(検索エンジン最適化)を適切に行うことで、以下のメリットが得られます。
✅ 広告費をかけずに患者さんを集められる
✅ 「信頼できる病院」として認識される
✅ 競合クリニックより先に患者さんの目に入る
SEOの詳しい仕組みや対策方法については、別記事で詳しく解説しています!
医療マーケティングの注意点
医療機関の広告には、厚生労働省の「医療広告ガイドライン」による規制があります。
違反すると指導や罰則の対象になるため、特に以下の点には注意しましょう。
🚫 誇大広告の禁止(「絶対に治る」「日本一の医師」などはNG)
🚫 体験談の掲載禁止(「この治療で完治しました!」などはNG)
🚫 比較広告の禁止(「当院の治療成績は他院より優れています」はNG)
まずは「何がOKで、何がNGなのか」を知ることが大切です。
医療広告ガイドラインについては、別で詳しく解説しています。
まとめ:初心者でも大丈夫!まずはここから始めよう
✅ マーケティングは「患者さんに価値を届ける仕組みづくり」
✅ まずは「現状を知る」ことから始める
✅ 目標を決め、できることから手を動かしてみる
未経験から医療マーケティングを始めると、不安や戸惑いも多いですが、少しずつできることから積み上げていけば、必ず成長できます。
次のステップとして、次回は『現状を知る』ための具体的な方法について解説します。
ぜひ参考にしてください!